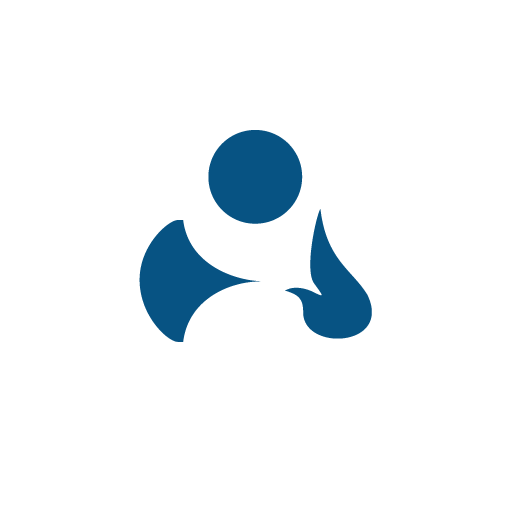Japanese Antique Box Table/箱膳 お膳 テーブル ちゃぶ台 収納 アンティーク 古道具 和家具
Thank you SoldOut
在庫切れ
説明
Japanese Antique Modern

江戸時代から昭和初期まで使われていた箱型のお膳、“箱膳(はこぜん)”
ちゃぶ台が主流となる明治時代中期までは一般的に使われていました。
小学生に上がるころの年齢になると一人一台、自分専用の箱膳を使って食事をしていたと言われています。
箱の中には一人分のお茶碗や小皿、お箸などを収納し、食事をする時に蓋を裏返してお盆のように箱の上に乗せ、その上に器を並べて食事をします。
そして食事が終わるとお茶碗にお湯を注ぎ、たくあんなどのお漬物でお椀についたご飯を拭う、そしてそのお湯を飲み、お漬物も食べる。
そのあとふきんで器をきれいに拭き上げると、箱の中に収納します。
現代ではなかなか想像できませんが、水洗いはひと月に数回ほどだったのだとか。

This box-shaped table is old Japanese furniture.


こちらの箱膳は欅材で作られた、引き出しのあるタイプ。
100年ほど前の庶民の食事は”一汁一菜”だった言われており、それを並べるには十分なサイズの立方体で小ぶりな物が多い印象があります。
しかしこちらは長方形でやや大きなサイズの箱膳。
”一汁一菜”どころか、”一汁三菜”も余裕で並べられるサイズです。
少し裕福な家庭で使われていた物なのか、もしくはより現代に近い時代に使われていた物なのか…
古い家具はこんなふうに使われていた時代の背景を想像するのも、なんだかワクワクしますね。


蓋の表面のまわりに浅い彫り込みがあるのは、蓋を裏返して食事をするときに出っ張った部分が箱の内側にはまり、箱からズレないようにするためのものだそうです。
ほんの少しの工夫ですが、これがあるのとないのではだいぶ使い心地も変わりそうです。
力強く美しい欅材の杢目を活かした作りに当時の職人さんの粋な仕事ぶりが現れています。



SHOW
DIMENSIONS


古い塗料を洗浄、クリーニング後、サンディングをいたしました。
背面の角にパテ埋めによる補修跡がございます。
引き出し内、蓋内にシミ汚れ、また、若干古い木材のにおいを感じます。
蓋内の底面に浮きがございます。
古いもののため、経年や使用に伴う傷や擦れがございますが、大きなダメージはございません。


ちゃぶ台や文机など、当時の人々に少し倣った使い方以外にも、テレビ台にしてしまうというなんとも現代的な使い方もアリ。
歴史とロマンが詰まった古道具は日本の古い文化やならわしを現代にいながら肌に感じることができます。
古道具の新しい使い方やコーディネートを探してみるのもきっと楽しいはず…♪


【サイズ】
全体 横幅 57.7cm 奥行 43m 高さ 25.8cm
蓋内寸 横幅 53cm 奥行き 38.5cm 高さ 10.5cm
引き出し内寸 横幅 22cm 奥行き 37cm 高さ 8.4cm(左右共に同じ内寸)
【材質】欅材
【年代】江戸時代〜昭和初期(推定)
【配送方法】
ヤマト運輸もしくは自社便をお選びいいだけます。
他社便の配送料はカートページよりご確認ください。
・ヤマト宅急便160サイズ
・自社便配送料(着払い)[Aエリア]1000円[Bエリア]2000円
※[Cエリア]はヤマト宅急便での配送となります。
Feel warmth and texture
WEBでのご紹介にあたって、可能な限り詳細をお伝えできるよう努めておりますが、当店での取り扱い商品は、ビンテージ品、ユーズド品の為、経年による状態の風合いや質感などの全てがお伝えできない部分がある場合がございます。WEBでの購入を検討されているお客様で、その他の詳細をご希望の方はお気軽に問い合わせください。
Store information
Address
Vintage&Secondhand Interior Shop FURUICHI/古一
〒166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1−28−8 1F
Tel · E-mail
お電話でのお問い合わせは下記電話番号までおかけください。
TEL : 03-5356-7362
メールアドレスでのお問い合わせはこちらへ
MAIL :
contact@usedfuruichi.com
Estimate
古一では無料の出張見積を行っております。ビンテージ家具・インテリア雑貨・USED品・ランプ等その他幅広く取り扱いをしております。杉並区周辺はもちろん、世田谷区・目黒区・武蔵野市・新宿区等の東京近郊にも無料にてお見積もりにお伺いいたします。またお店への持ち込みも大歓迎ですので、お気軽に03-5356-7362又はcontact@usedfuruichi.comにご連絡ください。
Related products
-
Swedish Vintage Royal Board Small Sideboard/スウェーデン ヴィンテージ ロイヤルボード スモールサイドボード テーブル チーク材 北欧家具
SoldOut -
Danish Vintage Teak Wood Side Chest/デンマーク ヴィンテージ チーク材 サイドチェスト 北欧家具
SoldOut -
Japanese Vintage Teakwood Slim Chest/ジャパン ヴィンテージ スリムチェスト チーク材 レトロモダン 北欧スタイル 収納家具
SoldOut -
Danish Vintage Side Chest 2drawer/デンマーク ヴィンテージ サイドチェスト
SoldOut
追加情報
| Made | Japan |
|---|